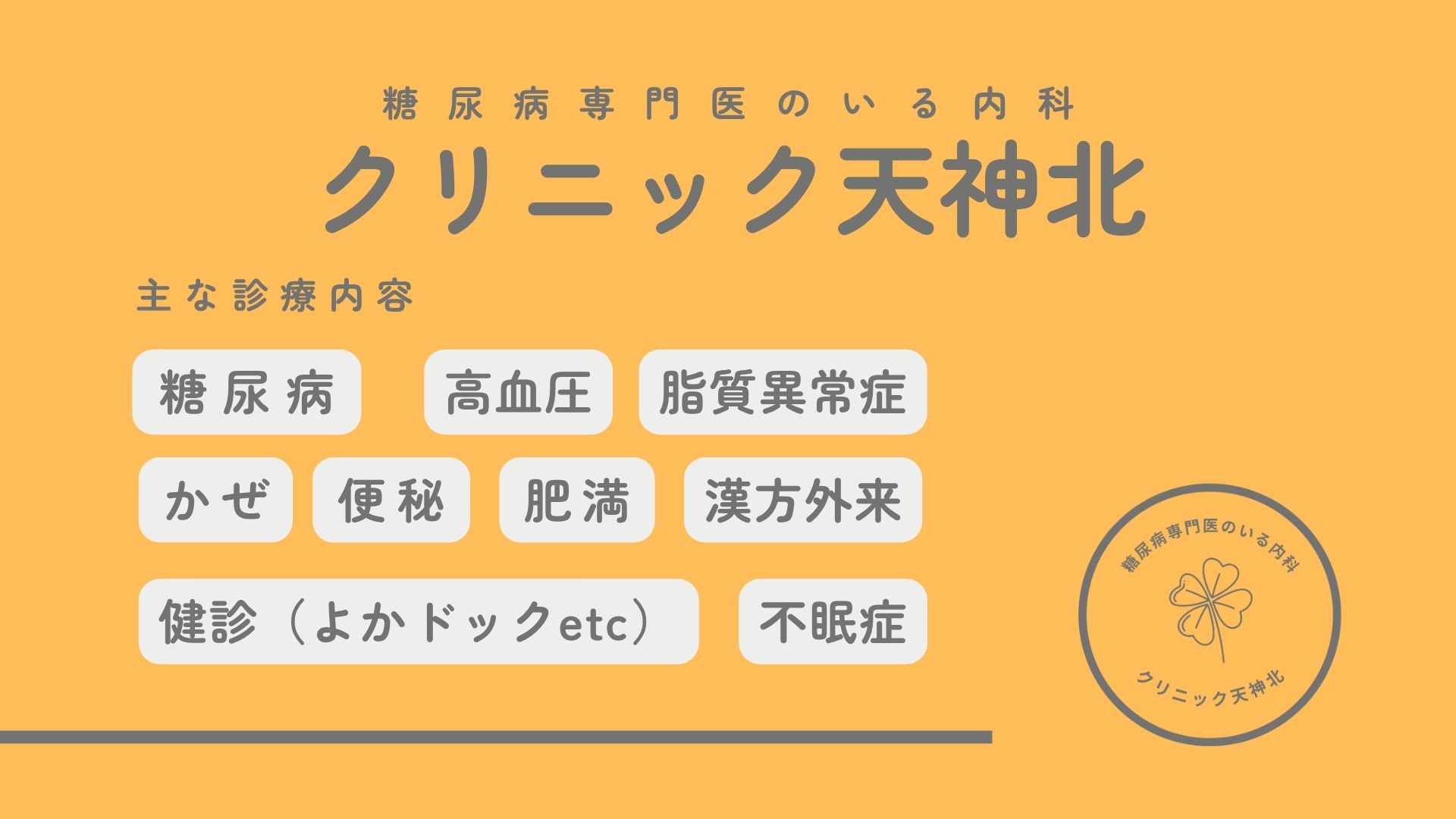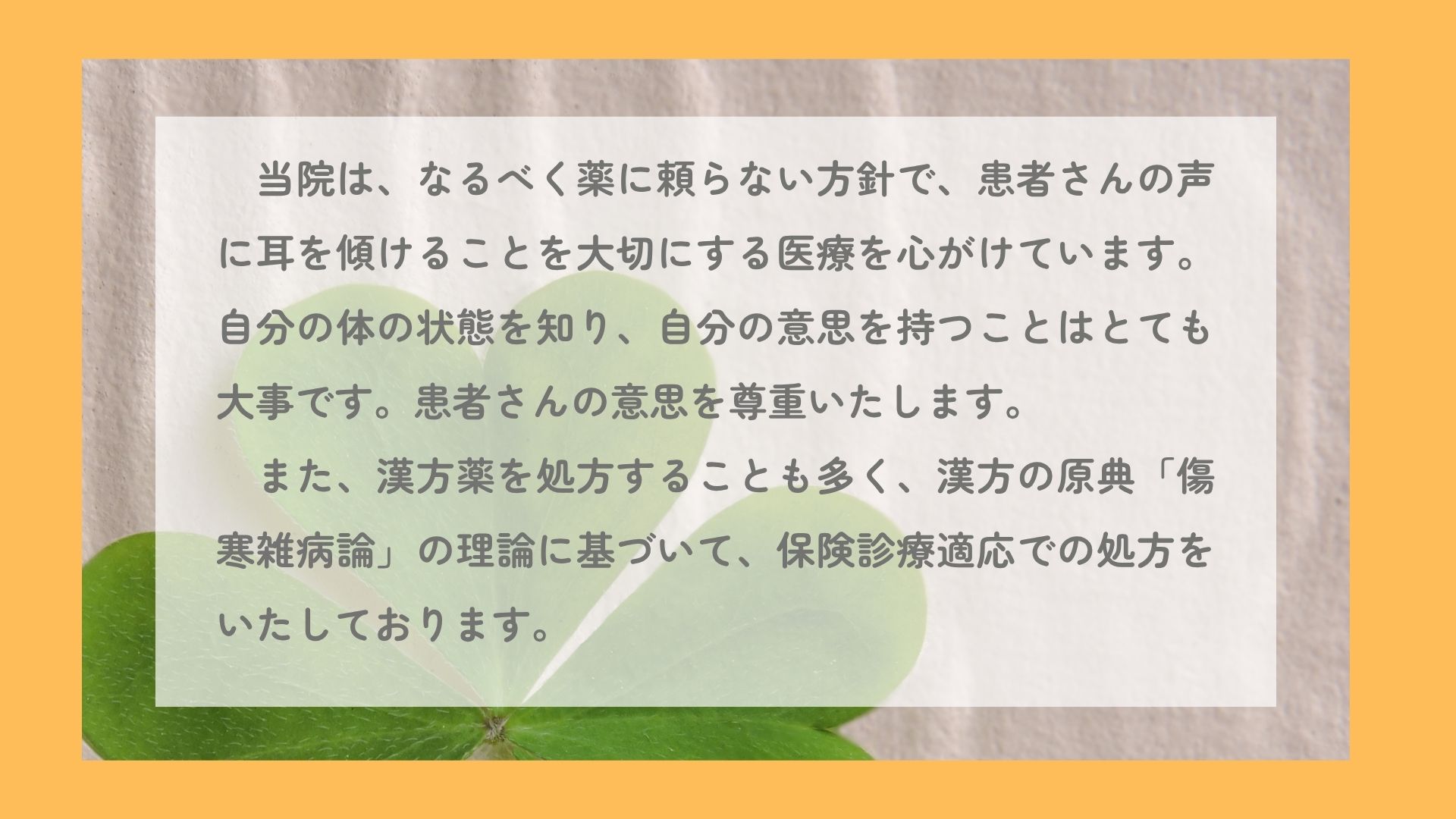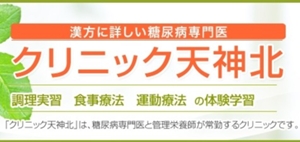今日中に風邪を治してください No4 2020,7.28 2021,10.27改
桂枝湯とはいかなる方剤なのでしょうか?主に真皮に残存した邪気(病原体の残骸など)を一掃し、乱れた組織を元の状態に戻す力を持つ方剤だと考えます。
邪気(ウイルスなど)が膀胱経に侵入し、経脈に従って流れて行き、表に広がっていきます。邪気を追って、陽気も表に広がっていきます。表の運動エネルギーが増加するので発熱します。胃へも陽気が流れて行きますが、遅れるため表の陽気の増加量が大きく、悪寒あるいは悪風を感じます。
胃壁内へ陽気が入り込み乱れると、心と肺へ陽気が多く流れて行きます。また、肝へも多くの陽気が流れ、肝気の乱れが起きます。これらの結果、門脈血の肝への流入が阻まれ、肝は常態を維持出来なくなります。
発汗の条件は満たされていますが、質的に十分な血液が病変部へ届かないため、病は治らないのです。
↘
缺盆 ----->;胆経脈
↓ ↘ ----->;脾経脈
↙期門-↓----->胃
↘ ↑ ↘ ↓
日月 肝<---脾
↙↑ 門脈血
甘草で 胃壁内へ導いた陽気を均一に分布させます。生姜で水の状態を整え、陽気を胃から脾へ送ります。大棗で肝へ流れる陽気を抑制し、芍薬で肝の陰を増やし陽を減らすことで、肝を落ち着かせます。桂枝で心を動かせば、質、量共に十分な血液を送り出して、表の不要物(不活化した邪気など)を処理できます。最後に、発汗させ、表の陰陽を整えれば病は治ります。
条文12の方後注に、熱いお粥を啜って衣服で覆って汗を出せと書かれています。桂枝湯の発汗作用は弱いと思われます。
*脾は脾臓ではありません。その主要部分は、小腸の絨毛を含んだ粘膜です。